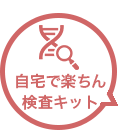>
予約確認はこちら
お知らせ
-
年末年始休暇のお知らせ
年末年始休暇のため、下記の日程を休診とさせていただきます。12月31日(水)~1月3日(土)1月4日(日)より、診察を行います。※日曜診療対応となります(内科・皮膚科)ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 -
医療DX推進の体制に関する事項について
当院では、質の高い診療を提供するために以下の取り組みを行っております。 ・当院ではマイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有しております。 ・オンライン資格確認システムを通じて、患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導を行う際、当該情報を閲覧し活用しています。 マイナンバーカードによる保険情報、医療情報、薬剤情報を取得し、その情報を活用して質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。 ・電子カルテ情報共有サービスを利用する取り組みを予定しております。 ・医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームぺージに掲載しています。 -
夏季休暇のお知らせ
ヒロクリニック心療内科は2025年8月11日(月)~2025年8月14日(木)まで夏季休診日とさせていただきます。 -
診療時間変更のお知らせ
平素より当クリニックをご利用頂き、誠にありがとうございます。 2025年6月9日より診療時間に変更がございますので、下記の通りお知らせいたします。 新しい診療時間は下記の通りとなります。 2025年6月9日より 【変更前】・月曜、火曜、水曜、金曜、土曜、日曜日:AM9:00~12:00 PM13:30~18:00 【変更後】・月曜、火曜、水曜、金曜、土曜、日曜日:AM9:00~13:00 PM14:30~18:00 -
保険診療の予約制度についてのお知らせ
このたび、より多くの患者様に柔軟にご利用いただけるよう、保険診療における「予約制度」を廃止し、 受付時間内にご来院いただく形へ変更させていただくこととなりました。 今後は、ご来院いただいた順にご案内させていただきますので、受付時間内に直接ご来院くださいますようお願いいたします。 引き続き、皆様により安心してご利用いただけるクリニックを目指してまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 -
(変更)4月27日より外部からの時間予約は取れなくなりました。
関係者各位へ ヒロクリニックでは今後時間予約を廃止いたします。これまでに予約のない方は来院してもらったのちに順番で診察を行います。電話での予約も行なっておりません。診察時に先生からまたは本人からの申し出があった場合には予約をクリニック内で取ることは可能です。 -
【お知らせ】14日~15日一部時間帯における電話受付について
4月14日~15日、当院のコールセンターが所在する地域にて、計画停電が実施されます。 これにより、停電の時間帯には2~3時間ほどお電話がつながらない状況となる見込みです。 なお、停電の開始時刻は現地でも未定となっており、事前のご案内が難しい状況です。 あらかじめご了承ください。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 停電が解消され次第、お電話対応を通常通り再開いたします。 お急ぎの際は、お問い合わせフォームまたはメールにてご連絡いただけますようお願いいたします。 -
2025年 ゴールデンウイーク期間中の診療について
ゴールデンウィーク期間中は暦通りの診療を行っており、土・日・祝日、振替休日(4/27,29,5/1,5/3,5/4,5/5,5/6)のみ、お休みとなります。 4/28,30 5/2は診療を行います。
こんなお悩み1人で抱えていませんか?





ヒロクリニック 心療内科では、うつ病、適応障害、睡眠障害、パニック障害、自律神経失調症、強迫性障害、摂食障害、統合失調症、認知症などの精神疾患全般を対象に治療を行っております。

患者様おひとりおひとりの病状とご希望を把握し、親切丁寧で無駄のない治療を心がけております。 患者様本人だけでなく、ご家族の不安も取り除けるよう力を尽くしていきます。 ご心配があればご家族も一緒におこし下さい。 皆さまが少しでもこころの健康を取り戻せるよう、スタッフ一同、全力を尽くして参ります。
自閉症スペクトラム障害(ASD)遺伝子検査について
自閉症スペクトラム障害(ASD)の遺伝子検査は、患者の遺伝的リスクを詳細に分析する先進的な手法です。この検査は、特定の遺伝子変異を検出し、自閉症スペクトラム障害(ASD)の傾向を早期に把握することができます。早期発見によって、適切な支援と介入計画を立てることができ、遺伝子検査は子どもたちの発達支援において重要な役割を担います。
遺伝子検査によって得られた結果とリスクには、専門の知識が必要です。そのため、医師や遺伝カウンセラーの協力が不可欠となります。検査結果に基づいて、医師は適切な治療を行い、専門的なアドバイスやサポートも提供しています。

自閉症スペクトラム障害(ASD)の遺伝的リスクを早期に特定することで、子どもの可能性を最大限に引き出し、発達障害の予防や軽減、リスク管理にもつなぐことができます。さらには子どもの健やかな成長と社会への適応を助ける一助にもなります。
※自閉症に関わる遺伝子のうち、特定の遺伝子を検査するものです。
初診の患者さまへ
可能な限り早く受診できるように尽力しております。 また、初診の患者さまには、事前にインターネットでの問診票へのご記入をお願いしております。
インターネットでの問診票へのご記入を利用することにより、混雑緩和にご協力いただくようお願いいたします。
- 事前記入のメリット
- ① ゆっくりと時間をかけて、自宅で問診内容を考えることができる。
- ② 問診内容をそのままカルテに記載されるので間違いがない。
- ③ メールアドレスが登録されるため、クリニックからの重要な変更およびお知らせが届く。

保険診療外の場合、クレジットカードでのお支払いが可能です

当院では保険診療外の場合、クレジットカードでのお支払いが可能です。
対応しているカードは「Visa」「Master Card」「JCB」「アメリカン・エキスプレス」「ダイナースクラブ」「銀聯(ギンレイ)カード」になります。
クレジットカード払いを希望される際は受付スタッフまでお気軽にお申し付けください。
コラム
統合失調症と就労継続支援A型の実情
2025年10月22日 心療内科
統合失調症を抱える人にとって、「働くこと」は治療と同じくらい大切なテーマです。安定した収入を得ることは生活の自立につながるだけでなく、社会参加や自己肯定感の回復...
統合失調症の社会的スティグマを考える
2025年10月22日 心療内科
統合失調症は、幻覚や妄想といった症状を特徴とする精神疾患であり、適切な治療と支援によって安定した生活を送ることが可能です。しかし、いまだに社会には「怖い」「危険...
統合失調症と運動習慣がもたらす効果
2025年10月22日 心療内科
統合失調症の治療と聞くと、「薬物療法」や「カウンセリング」を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし近年、世界的に注目されているのが「運動療法(エクササイズ・セラピ...
統合失調症患者のための家族教育入門
2025年10月22日 心療内科
統合失調症の治療は、患者本人だけでなく家族の理解と協力が欠かせません。症状が安定しても、再発やストレスによる悪化を防ぐためには、家族が病気の特性や支援の方法を正...