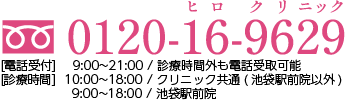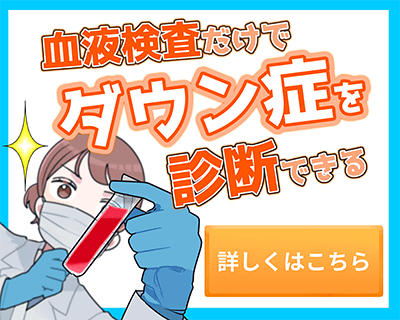妊娠後には流産の不安があります。初期に起こった流産のほとんどの原因が赤ちゃんの遺伝性疾患、先天性異常が原因です。NIPT(出生前診断)は母体からの採血で胎児の染色体異常を調べることが出来ます。胎児の状態に不安がある妊婦が任意で受ける検査です。
妊娠が分かった喜びとともに、流産への不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
流産は決して珍しいことではありませんが、その原因については誤解も少なくありません。
本記事では、流産の確率や医学的な原因、症状や治療法まで解説します。
ぜひ正しい知識を得て、ご自身の不安を和らげるためにお役立てください。
流産とは
流産とは、妊娠22週未満で妊娠が終結してしまう状態を指します。
日本産科婦人科学会の定義では、胎児が母体外で生存できない時期での妊娠終結とされています。
妊娠初期の女性にとってもっとも心配な出来事の1つですが、実は多くの妊娠で起こる自然現象です。
流産の約85%は妊娠12週未満の早期流産で、その大部分は胎児の染色体異常が原因です。
母体の年齢、健康状態、生活習慣なども影響しますが、多くの場合は予防が困難な自然淘汰として起こります。
正しい知識を持つことで、過度な自責の念を抱かずに適切な対応ができるようになります。
>>関連記事はこちら「化学流産とは?流産の種類と原因について【医師監修】」
流産が起こる確率
流産は全妊娠の約15%で発生し、高齢になるほど流産の確率は高まります。
妊娠に気づく前の化学流産を含めると、全妊娠の30~40%で何らかの流産が起きているとされています。
妊娠6~7週での心拍確認は、その後の妊娠継続にとって重要です。
また、1回流産を経験したあとでも、多くの女性が健康な赤ちゃんを出産しており、希望を持って次の妊娠に臨めます。
流産経験者の多くが、その後健康な赤ちゃんを出産している事実を知っておくことは大切です。
>>関連記事はこちら「妊娠から出産まで胎児の成長過程とNIPT(新型出生前診断)について【医師監修】」
こちらの動画では流産について、流産の主な原因に関して解説しておりますので、是非参考にしてください。
流産が起こる原因
流産の原因は多岐にわたりますが、とくに妊娠初期の流産のほとんどは胎児側の問題によるものです。
そのため、お母さんの行動が直接の原因となるケースは多くありません。
ここでは、流産を引き起こす可能性があるとされる、以下6つのおもな原因について解説します。
- 原因①胎児の染色体に異常がある
- 原因②内分泌疾患がある
- 原因③子宮に異常がある
- 原因④感染症にかかっている
- 原因⑤生活習慣に問題がある
- 原因⑥精液所見に異常がある
これらの原因を正しく理解し、過度に自分を責めないことが大事です。

原因①胎児の染色体に異常がある
流産原因の60~80%を占める胎児の染色体異常は、受精時にランダムに発生する自然現象です。
モノソミー(染色体が1本少ない状態)といった異常も起こり、これらの多くは生命と両立しないため、自然淘汰として流産に至ります。
母体の年齢が上がるほど卵子の染色体異常リスクが増加し、35歳以上では急激に上昇します。
染色体異常による流産は予防が難しいですが、ご自身を責めすぎず、必要なサポートを受けて過ごされることが大切です。
原因②内分泌疾患がある
甲状腺機能異常、糖尿病などの内分泌疾患は、ホルモンバランスを乱し流産リスクを高めます。
甲状腺機能低下症も流産リスクを高めますが、適切な治療により改善できます。
糖尿病では血糖コントロール不良により、胎児の発育遅延を起こすことも。
黄体機能不全では、妊娠維持に必要なプロゲステロンが不足し、子宮内膜の維持が困難になります。
これらの疾患は血液検査で診断可能で、多くは薬物療法により管理できます。
妊娠前から適切な治療を受けることで、流産リスクを大幅に減少させられるため、計画的な妊娠準備が肝要です。
原因③子宮に異常がある
子宮筋腫や子宮奇形などの子宮の構造的異常は、着床障害や胎児への血流不足を引き起こします。
子宮筋腫は30歳以上の女性の20~40%にみられますが、とくに粘膜下筋腫や筋層内筋腫は流産率が高い傾向です。
子宮頸管無力症では、妊娠中期に子宮口が開いてしまい、後期流産の原因となります。
これらの異常は超音波検査などで診断でき、手術療法により改善可能な場合も多いため、妊娠前の検査が推奨されます。
原因④感染症にかかっている
細菌性膣症やクラミジア、トキソプラズマなどの感染症は、子宮内感染により流産を引き起こす可能性があります。
とくに細菌性膣症は流産リスクを高める可能性があります。
性感染症は無症状のことも多く、定期的な検査が欠かせません。
風疹やサイトメガロウイルスなどのウイルス感染も胎児に影響を与えます。
妊娠前のワクチン接種、適切な衛生管理、早期の感染症治療により、これらのリスクは予防可能です。
パートナーも含めた感染症対策が、健康な妊娠継続につながります。
原因⑤生活習慣に問題がある
喫煙や過度の飲酒、カフェインの過剰摂取などの生活習慣は、流産リスクを有意に増加させます。
喫煙は流産リスクを高め、受動喫煙も同様です。
アルコールは胎児の発育を阻害し、とくに妊娠初期の摂取は危険です。
カフェインの過剰摂取もリスクを上昇させ、肥満(BMI30以上)も流産リスクを高めます。
不規則な生活や栄養不足も影響します。
これらの要因はすべて改善可能であり、妊娠前からの生活習慣の見直しが、健康な妊娠の第一歩です。
原因⑥精液所見に異常がある
精子の質の低下も流産の一因となることが、近年の研究で明らかになっています。
精子DNAの損傷は、受精後の胚発育に影響を与え、流産に大きく影響を与える要素です。
精子の運動率低下や奇形率の上昇、精子濃度の低下も関連があり、男性の加齢やストレス、不規則な生活習慣などが精子の質を低下させます。
とはいえ、禁煙と適正体重の維持、規則正しい生活など健康的な生活習慣により、改善が期待できます。
また、精索静脈瘤がある場合は適切な治療によって、精液所見の改善が可能です。
不妊治療を受ける際は、女性だけでなく男性側の検査も肝心であり、夫婦で協力して取り組むことが大切です。
流産の分類
流産はさまざまな観点から分類され、それぞれ異なる対応が必要です。
ここでは、以下4つの分類方法について説明します。
- 原因による分類
- 症状・所見による分類
- 進行度による分類
- 回数による分類
これらの分類を理解することで、自身の状況を正確に把握できます。
原因による分類
流産は原因により、以下のように大別されます。
| 分類 | 内容 | 詳細 |
| 自然流産 | 意図せず起こる流産 | 全流産の大部分を占める胎児要因(染色体異常など)母体要因(子宮異常、内分泌疾患など) |
| 人工流産 | 医学的理由や母体保護法に基づく妊娠中絶 | 医学的適応による中絶母体保護法に基づく処置 |
| 原因不明 | 現在の医学では解明できない複合的要因 | 不育症の半数以上が該当複数の要因が関与している可能性 |
| その他の分類 | 詳細な原因別分類 | 感染性流産内分泌性流産免疫性流産 |
原因に応じた治療や予防策が検討され、原因を特定することで次回妊娠での対策が立てやすくなります。
症状・所見による分類
臨床症状により、以下のように分類されます。
| 分類 | 症状・所見 | 対応 |
| 切迫流産 | 出血や腹痛がある妊娠継続可能な状態胎児心拍は確認できる | 安静により改善することが多い経過観察が中心 |
| 稽留流産 | 自覚症状なし胎児が子宮内で死亡している状態 | 定期検診で発見される待機療法か手術を選択 |
| 進行流産 | 子宮口が開いている流産が避けられない状態出血・腹痛が強い | 積極的な処置が必要感染予防が重要 |
| 完全流産 | 胎児組織が完全に排出された状態出血は減少傾向 | 経過観察のみ追加処置は不要 |
| 不全流産 | 胎児組織の一部が子宮内に残存持続的な出血がある | 子宮内容除去術が必要感染リスクに注意 |
| 化学流産 | 妊娠反応陽性後、胎嚢確認前に終結極早期の流産 | 特別な処置は不要正式な流産回数に含めない |
それぞれの状態により、経過観察か積極的治療かの判断が異なります。
>>関連記事はこちら「【医師監修】切迫流産とは?原因・兆候・予防法|妊娠初期に注意したい症状も紹介」
進行度による分類
流産の進行度は、可逆的な段階から不可逆的な段階まで連続的に変化します。
初期段階の切迫流産では、適切な安静と治療により妊娠継続が期待できる場合が多いです。子宮口が閉鎖している限り、妊娠継続の可能性があります。
進行流産に移行すると、子宮口が開大し羊膜が破綻するため、流産は避けられません。
この段階では感染予防と適切な処置が重要です。
稽留流産では胎児心拍が停止していますが、自然排出を待つか手術を選択するかの判断が必要です。
完全流産後は経過観察のみで済みますが、不全流産では追加処置を要することがあります。
進行度の正確な評価が、適切な管理につながります。
回数による分類
流産の回数により、以下のように分類されます。
| 分類 | 定義 | 発生率 | 対応・特徴 |
| 散発流産 | 1回の流産 | 全妊娠の約15% | 一般的な現象特別な検査は不要次回妊娠成功率85~90% |
| 反復流産 | 2回連続の流産 | 2~5% | 日本では不育症検査開始を推奨原因検索が重要次回妊娠成功率約80% |
| 習慣流産 | 3回以上の連続流産 | 約1% | 不育症として専門的治療対象詳細な検査が必要次回妊娠成功率約70% |
流産回数が増えても、適切な治療により生児獲得は可能です。
回数による分類は、検査開始時期と治療方針の決定に重要な指標となります。
流産が起きるときに見られる兆候や症状
流産が起こる際のもっとも一般的な兆候は、「性器出血」と「下腹部痛」です。
出血は、茶色っぽいおりもの程度の少量から、月経時よりも多い鮮血までさまざまです。
下腹部痛も、生理痛のような鈍い痛みから、強いけいれん性の痛みまで個人差があります。ただし、妊娠初期には着床出血など、流産とは関係のない出血も起こりえます。
また、稽留流産のように、自覚症状が全くないまま進行するケースも少なくありません。
気になる症状があれば、自己判断せずに医療機関に相談しましょう。
流産の診断方法
流産の診断は、おもに「経腟超音波(エコー)検査」によって行われます。
この検査では、子宮内に胎嚢(たいのう)と呼ばれる赤ちゃんの袋が確認できるか、胎嚢の中に胎芽(たいが)や心拍が見えるかを調べます。
週数に応じた胎児の大きさがなく、心拍が確認できない場合に流産の可能性が考えられるでしょう。
補助的な診断として、血液検査でhCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)という妊娠ホルモンの値を測定することもあります。
流産の治療方法
稽留流産や不全流産と診断された場合、子宮内に残った組織をどうするかを決定する必要があります。
おもな選択肢は、自然な排出を待つ方法と、手術によって内容物を取り除く方法の2つです。
どちらの方法を選ぶかは、妊娠週数や母体の健康状態、そしてご本人の希望を考慮して決定します。
ここでは、以下2つの治療法について解説します。
- 自然排出
- 流産手術
どちらの方法にも利点と欠点があるため、医師と十分に相談し、納得のいく選択をすることが大切です。
自然排出
自然排出は、手術を行わず、子宮内容物が自然に出てくるのを待つ方法です。
月経のような出血と腹痛が起こり、数日から数週間かけて排出されます。
身体的な負担が少なく、子宮に器具を入れないため損傷のリスクがない点が利点です。
一方で、いつ排出が始まるか予測できず、日常生活に影響が出ることがあります。
出血量が多くなったり、痛みが強くなったりする可能性も否定できません。
排出が不完全で、最終的に手術が必要になるケースもあります。
流産手術
流産手術は、子宮内に残った胎嚢や胎盤などの組織を、器具を用いて取り除く方法です。
現在では、子宮内膜への負担が少ない「手動真空吸引法(MVA)」を導入している医療機関もあります。
手術日が決まっているため計画的に治療を進められ、自然排出に比べて出血期間が短く、精神的な負担が軽減される点が利点です。
ただし、麻酔や手術に伴うリスク(感染、子宮穿孔など)がゼロではありません。
妊娠初期の流産のリスクを下げるためにできること
妊娠初期の流産の多くは胎児の染色体異常が原因であり、残念ながら予防することは困難です。
しかし、母体側の要因による流産のリスクを少しでも減らすために、妊娠中の健康管理は肝心です。
ここでは、お母さん自身が赤ちゃんの育つ環境を整えるためにできる、以下4つを紹介します。
- 妊婦健診を定期的に受ける
- 禁煙する
- 禁酒する
- 適正体重をキープする
これらの実践が直接的に流産を防ぐわけではありませんが、健やかな妊娠期間を送るための大切な基盤となります。
妊婦健診を定期的に受ける
定期的な妊婦健診は、母体と赤ちゃんの健康状態をチェックするために不可欠です。
健診では、超音波検査で赤ちゃんの成長を確認するだけでなく、お母さんの血圧や体重、尿検査なども行います。
これにより、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病、感染症といった流産のリスクとなりうる異常を早期に発見可能です。
万が一、子宮や胎盤に問題が見つかった場合でも、早期に対応することでリスクを管理できる可能性があります。
健やかな妊娠・出産のために、必ず指定されたスケジュールで受診しましょう。
禁煙する
妊娠中の喫煙は、流産のリスクを高める要因の1つです。
タバコに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があり、胎盤への血流を悪化させます。
その結果、赤ちゃんに十分な酸素や栄養が届かなくなり、発育不全や流産につながる危険性が高まります。
パートナーが吸うタバコの煙(受動喫煙)も同様に有害です。
赤ちゃんを守るためには、妊婦さん自身の禁煙はもちろん、家族全員の協力が不可欠です。妊娠を考え始めた段階から、禁煙に取り組むことが強く推奨されます。
禁酒する
妊娠中のアルコール摂取は、流産のリスクを高めるだけでなく、胎児の発育に深刻な影響を与える「胎児性アルコール症候群」の原因となります。
アルコールは胎盤を通過しやすく、赤ちゃんの脳や身体の正常な発達を妨げます。
妊娠中に安全とされる飲酒量は明らかになっていないため、たとえ少量であっても控えることが望ましいです。
ビールやチューハイなど、アルコール度数が低いお酒も同様に控えましょう。
妊娠が判明した時点から、出産・授乳が終わるまで、完全な禁酒を徹底することが赤ちゃんの健康を守るためにも肝要です。
適正体重をキープする
妊娠前の体重管理も、流産のリスクに影響します。
とくに肥満は、糖尿病や高血圧を合併しやすく、血栓症のリスクも高まるため、流産だけでなくさまざまな妊娠合併症の原因となります。
妊娠が分かったら、急激なダイエットはせず、医師や助産師の指導のもとで適切な体重増加を目指しましょう。
バランスの取れた食事と適度な運動が、健康な体作りの基本です。
>>関連記事はこちら「妊娠中に食べた方が良いもの・気をつけたいもの【医師監修】」
妊娠後期の流産のリスクを下げるためにできること
妊娠12週から22週未満に起こる「後期流産」は、初期流産とは異なり、子宮頸管無力症や感染症といった母体側の原因が多くなります。
そのため、日常生活での過ごし方に気をつけることで、リスクをある程度下げられるかもしれません。
ここでは、妊娠中期以降にとくに意識したい、以下6つの生活習慣について解説します。
- 重いものを持つ行為を控える
- バランスのよい食事を心がける
- 性行為の際はコンドームを必ず着用する
- 過度な運動は控える
- 姿勢に注意する
- 長時間の入浴は控える
無理のない範囲で、お腹の赤ちゃんを守る生活を送りましょう。
重いものを持つ行為を控える
お腹に強い圧力がかかると子宮が収縮し、切迫流産や早産のリスクを高めることがあります。
そのため、重いものを持つ行為はできるだけ避けましょう。
とくに、上の子どもの抱っこや、買い物での重い荷物運びには注意が必要です。
どうしても必要な場合は、膝を曲げて腰を落とし、お腹に力が入らないようにゆっくりと持ち上げる工夫をしてください。
パートナーや周りの人に協力をお願いし、体に負担をかけないようにすることが大切です。お腹の張りを感じたときは、すぐに休むようにしましょう。
バランスのよい食事を心がける
バランスの取れた食事は、母体の健康を維持し、感染症にかかりにくい体を作る基本です。
鉄分やカルシウム、葉酸といった栄養素は、赤ちゃんの成長と母体の健康に不可欠なので、意識して摂取しましょう。
また、体重の急激な増加は、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群のリスクを高めます。
これらは後期流産の一因ともなるため、糖分や塩分の多い食事は控えめにすることが大切です。
規則正しい食生活を送り、体の内側から妊娠をサポートしましょう。
性行為の際はコンドームを必ず着用する
妊娠中の性行為は、必ずしも禁止ではありませんが、感染予防の観点から注意が必要です。
細菌が腟から子宮内に侵入すると、絨毛膜羊膜炎(じゅうもうまくようまくえん)という炎症を引き起こし、後期流産や早産の原因となることがあります。
これを防ぐため、性行為の際には必ず最初から最後までコンドームを着用しましょう。
また、精液に含まれるプロスタグランジンという物質には子宮を収縮させる作用があるため、お腹の張りを感じやすい場合は控えるべきです。
過度な運動は控える
妊娠中の適度な運動は、体重管理や体力維持に有効ですが、過度な運動は体に負担をかけます。
とくに、ジャンプを伴う動きや、他人と接触する可能性のある激しいスポーツ、転倒のリスクがある運動は避けるべきです。
息が切れるほど激しい運動や、お腹に力が入るような筋力トレーニングも控えましょう。
ウォーキングやマタニティスイミング、ヨガなど、医師に相談したうえで、体に負担の少ない運動を無理のない範囲で行うのがおすすめです。
体調が優れない日は、勇気を持って休みましょう。
姿勢に注意する
妊娠中期以降はお腹が大きくなるため、体の重心が変わり、姿勢が崩れやすくなります。
同じ姿勢や長時間の立ち仕事、無理な姿勢を続けると、腰痛の原因となるだけでなく、お腹の張りを促し、流産につながる可能性もあります。
長時間同じ姿勢でいることを避け、デスクワークの合間には立ち上がって軽くストレッチをするなど、意識的に体を動かしましょう。
座るときはクッションなどを活用して、楽な姿勢を保つ工夫も効果的です。
血行をよくすることが、お腹の赤ちゃんにとってもよい環境につながります。
長時間の入浴は控える
リラックス効果のある入浴ですが、長時間の入浴や熱すぎるお湯は避けましょう。
体温が急激に上昇すると、血圧が変動したり、のぼせて転倒したりする危険があります。
お湯の温度はぬるめに設定し、入浴時間も10分程度を目安にすると安心です。
半身浴にしたり、脱衣所を暖めたりしておくなど、体に負担をかけない工夫をしながら、リラックスタイムを楽しみましょう。
流産後に再び妊娠できるのか
流産を経験すると、次に妊娠できるのか、また流産してしまうのではないかと不安に思う方は少なくありません。
しかし、一度の流産がその後の妊娠に影響することはまれです。
多くの場合、流産後も再び妊娠し、無事に出産できます。
身体の回復の目安として、通常は流産後4〜6週間ほどで月経が再開します。
そして、1〜2回月経が順調に来れば、子宮の状態は妊娠可能な状態に戻ったと考えてよいでしょう。
ただし、心と体の回復には個人差があります。
焦らず医師と相談しながら、ご自身のペースで次の妊娠を考えていくことが大切です。
流産のリスクに備えるならNIPT(新型出生前診断)を受けるのが理想
流産の最大の原因である胎児の染色体異常のリスクに備えるため、NIPT(新型出生前診断)という選択肢があります。
これは、お母さんからの採血のみで、お腹の赤ちゃんの染色体異常の可能性を調べる精度の高いスクリーニング検査です。
ここでは、NIPTの目的や検査内容について、以下3つの観点から紹介します。
- NIPTの目的
- NIPTで調べられること
- NIPTの注意点
検査について正しく理解し、ご自身の状況に合った選択をすることが肝心です。
NIPTの目的
NIPTのおもな目的は、妊娠の早い段階で、お腹の赤ちゃんの特定の染色体疾患に対するリスクを評価することです。
これにより、妊婦さんとそのご家族が、妊娠に関する情報をより多く得て、十分な情報に基づいて意思決定をする手助けとなります。
検査結果が陰性(リスクが低い)であれば、多くの妊婦さんは安心感を得られます。
一方、陽性(リスクが高い)の可能性があると分かった場合は、確定診断のための検査に進むかどうかを検討しましょう。
今後の妊娠・出産に向けて心の準備や、必要な医療体制を整える時間へとつながります。
NIPTで調べられること
NIPTでおもに調べられるのは、胎児の染色体の数の異常(異数性)です。
基本検査の対象となるのは、もっとも頻度の高い以下3つのトリソミー(染色体が1本多い状態)です。
これらの疾患は、流産の原因ともなりうるものです。
医療機関によっては、これらに加えて性染色体の異常や、染色体の一部が欠ける微小欠失症候群などを調べるオプションもあります。
NIPTの注意点
NIPTを受けるうえでもっとも重要な注意点は、この検査が「確定的検査」ではないことです。
NIPTはあくまで「スクリーニング検査」であり、染色体異常の「可能性が高いか低いか」を確率で示すものです。
精度は高いですが、偽陽性(陽性と判定されたが実際は異常がない)や偽陰性(陰性と判定されたが実際は異常がある)の可能性もごくわずかに存在します。
そのため、NIPTで陽性の結果が出た場合、診断を確定するためには、羊水検査などの確定的検査を受ける必要があります。
まとめ
流産は全妊娠の約15%で起こる現象ですが、その原因の多くは胎児の染色体異常による自然淘汰です。
適切な医学的ケアと心理的サポートにより、流産を経験された方でも次回妊娠での成功率は高く、希望を持って妊娠に臨めます。
ヒロクリニックNIPTでは、妊娠10週から採血のみで胎児の染色体異常を高精度で検出できるNIPT検査を提供。
6万4,000件以上の実績を持ち、国内検査により95%の方が8日以内に結果をお届けします。
羊水検査サポート制度により、陽性時も最大20万円まで補助を受けられるため、安心して検査を受けていただけます。
妊娠初期の不安を軽減し、適切な準備をするためにも、ぜひNIPT検査をご検討ください。
妊娠後には流産の不安があります。初期に起こった流産のほとんどの原因が赤ちゃんの遺伝性疾患、先天性異常が原因です。NIPT(出生前診断)は母体からの採血で胎児の染色体異常を調べることが出来ます。胎児の状態に不安がある妊婦が任意で受ける検査です。
記事の監修者
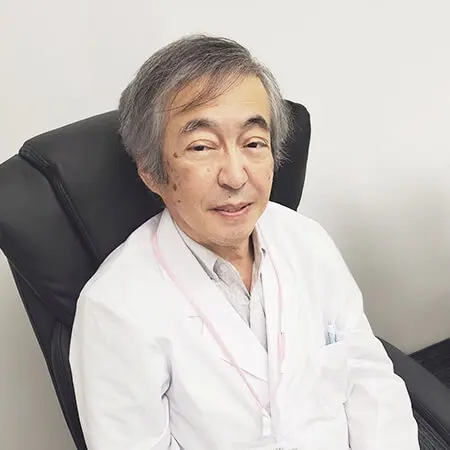
岡 博史先生
【役職】
【資格】
【略歴】
【所属】
【SNS】
 中文
中文