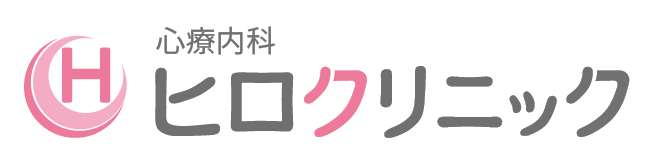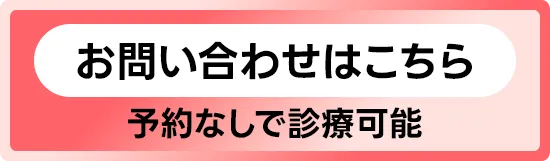Tags : 治療
仕事と心療内科通院を両立するスケジュール管理術
2026年1月21日 心療内科
仕事を続けながら心療内科へ通院することは、決して珍しいことではありません。うつ病、不安障害、パニック障害、適応障害、自律神経の乱れなど、心の不調を抱えながらも「...
心療内科医が勧める仕事と私生活のバランス改善法
2026年1月21日 心療内科
仕事の忙しさに追われ、「休んでいるのに疲れが取れない」「休日も仕事のことが頭から離れない」という悩みは珍しくありません。現代社会では、労働と私生活の境界が曖昧に...
心療内科医が勧める仕事と私生活のバランス改善法
2026年1月9日 心療内科
仕事の忙しさに追われ、「休んでいるのに疲れが取れない」「休日も仕事のことが頭から離れない」という悩みは珍しくありません。現代社会では、労働と私生活の境界が曖昧に...
統合失調症と就労継続支援A型の実情
2025年10月22日 心療内科
統合失調症を抱える人にとって、「働くこと」は治療と同じくらい大切なテーマです。安定した収入を得ることは生活の自立につながるだけでなく、社会参加や自己肯定感の回復...
統合失調症と運動習慣がもたらす効果
2025年10月22日 心療内科
統合失調症の治療と聞くと、「薬物療法」や「カウンセリング」を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし近年、世界的に注目されているのが「運動療法(エクササイズ・セラピ...
統合失調症患者が語る回復ストーリー
2025年10月22日 心療内科
統合失調症は長期的な治療を必要とする精神疾患のひとつですが、「回復できない病気」ではありません。かつて幻覚や妄想に苦しんだ人が、再び仕事に復帰し、家族や社会との...
統合失調症とストレス管理の実践的手法
2025年10月20日 心療内科
統合失調症は、幻聴や妄想などの症状が現れる精神疾患ですが、その背景には「ストレス脆弱性モデル」と呼ばれる考え方があります。つまり、ストレスが増すことで症状が悪化...
統合失調症とアルコール依存の複合課題
2025年10月20日 心療内科
統合失調症とアルコール依存症は、それぞれ単独でも重い精神疾患ですが、両者が併存する場合(いわゆるデュアルディスオーダー)には、症状の悪化、治療離脱、再発リスクの...
統合失調症と睡眠障害の深い関連を探る
2025年10月20日 心療内科
統合失調症は、幻覚や妄想、思考の混乱などを特徴とする精神疾患ですが、その背景には「睡眠障害」が深く関わっていることが近年の研究で明らかになっています。実際、統合...
統合失調症の治療で注目される新薬情報
2025年10月14日 心療内科
統合失調症の治療は、これまでドパミンを抑える薬が中心でした。しかし、陽性症状(幻聴・妄想)は改善しても、陰性症状(意欲低下・引きこもり)や認知機能の低下には十分...