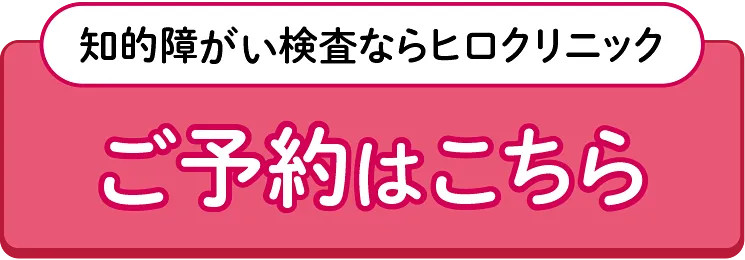NIPTで「陽性」なら中絶できるのか? 驚くべきことに、日本の母体保護法には「胎児の障害」を理由に中絶を認める条項(胎児条項)は存在しません。 法律上の答えは「No」でありながら、実態としては「経済的理由」として行われている「Yes」。この法的なねじれ(ダブルスタンダード)はなぜ起きるのか? NIPTを検討する前に知っておくべき「法の壁」と倫理的現実を、感情論抜きで徹底解説します。
1. 日本の法律における「中絶」と「胎児条項」の不在
NIPTと法律の関係を語る上で、最も重要かつ誤解されやすいのが「人工妊娠中絶」に関する法律、すなわち「母体保護法」と刑法の「堕胎罪」の関係です。
刑法上の原則:堕胎罪
まず大原則として、日本の刑法(第212条〜216条)には「堕胎罪」が存在します。胎児を母体外に排出させる行為は、原則として犯罪です。
しかし、これでは望まない妊娠や、母体の生命が危険な場合などに対応できません。そこで、特定の条件下においてのみ堕胎罪の違法性を阻却(免除)する特別法として存在するのが「母体保護法」です。
母体保護法第14条の壁
母体保護法第14条では、指定医師が中絶を行える条件として、主に以下の2つを定めています。
- 身体的・経済的理由: 妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがあるもの。
- 暴行・脅迫による妊娠: 強姦などによる妊娠。
ここに、「胎児に障害がある場合(胎児条項)」という文言は存在しません。
イギリスやフランスなど多くの欧米諸国では、「胎児に重篤な疾患がある場合」を中絶の適応条件として法律で明記しています。しかし、日本では過去の経緯(後述する優生保護法への反省)から、この条項が意図的に削除・回避されてきました。
「経済的理由」による拡大解釈の実態
では、NIPTで陽性判定(ダウン症候群など)を受け、羊水検査で確定した後、多くのカップルはどのようにして中絶を選択しているのでしょうか。
実務上は、「障害児を育てることは経済的に困難であり、母体の健康(精神的健康を含む)を害する」という解釈のもと、第14条第1号の「経済的理由」を適用して中絶が行われているのが現状です。
これは法的な「建前(障害を理由にはできない)」と「本音(障害を理由に中絶が行われている)」が乖離している状態であり、長年、日本の周産期医療における最大の倫理的・法的ジレンマとなっています。
医師はカルテに「胎児異常」とは書かず、「経済的理由」と記載することが通例となっており、この不透明さが、当事者の罪悪感を増幅させる一因ともなっています。
2. 歴史の影:旧優生保護法と「不良な子孫」の思想
なぜ日本には「胎児条項」がないのか。それを理解するためには、1948年から1996年まで存在した「旧優生保護法」の歴史を紐解く必要があります。NIPTを巡る議論は、常にこの歴史との闘いです。
旧優生保護法の目的
旧優生保護法は、戦後の人口爆発の抑制と、「不良な子孫の出生を防止する」という優生思想を目的として制定されました。
この法律の下では、遺伝性疾患や知的障害、精神障害のある人々に対し、本人の同意なしに不妊手術(優生手術)を行うことが国策として認められていました。
「障害者の排除」への反省と法改正
1990年代に入り、国際的な障害者の権利擁護運動の高まりを受け、1996年に「優生保護法」は「母体保護法」へと改正されました。この際、「不良な子孫の出生防止」という目的条項は削除されました。
この改正の過程で、「胎児に障害があるから中絶する」という考え方自体が、旧法の優生思想(障害者は生まれてくるべきではないという思想)に繋がると強く懸念されました。
その結果、障害者団体などからの強い反対もあり、「胎児条項」は導入されず、現在に至るまで「法律上は胎児の障害を理由にした中絶は存在しない」という形になっています。
最高裁判決と国の責任
2024年(令和6年)、最高裁判所は旧優生保護法を「憲法違反」とし、国に賠償を命じる判決を下しました。国は被害者に謝罪しましたが、この判決は「障害の有無によって個人の尊厳を侵害してはならない」という司法の強いメッセージでもあります。
NIPTによる選択は、個人の「自己決定権」であると同時に、一歩間違えれば「私的な優生思想」の実践になりかねないという危うさを孕んでいます。法律がNIPTに対して慎重な姿勢を崩さない背景には、この重い歴史があるのです。
3. 国際法との葛藤:障害者権利条約と国連からの勧告
視点を世界に移すと、NIPTと知的障害を巡る議論は、国際的な人権問題として扱われています。日本も2014年に批准した「障害者権利条約」が大きな鍵を握っています。
障害者権利条約とは
この条約は、障害者の固有の尊厳、自律、差別されない権利を保障するものです。「障害の社会モデル(障害は個人の心身機能ではなく、社会の障壁によって作られる)」という考え方を基礎としています。
国連障害者権利委員会からの勧告
2022年、国連の障害者権利委員会は、日本政府に対して初の対日審査勧告を行いました。その中には、出生前診断に関する以下のような懸念が含まれています。
- 「胎児の障害を理由とした中絶を可能にするような出生前検査の情報提供や、社会的な圧力を懸念する」
- 「障害のある胎児の中絶が、障害者への差別や偏見を助長しないよう対策を求める」
つまり、国際的な人権基準から見れば、NIPTで「障害があるから産まない」という選択が容易に行われる社会構造は、障害者の生存権を脅かす差別的なものであると指摘されているのです。
「知る権利」と「産まない権利」の対立
一方で、女性にはリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)があり、「産むか産まないかを自分で決める権利」や「胎児の状態を知る権利」があります。
- 女性の権利: 自分の人生設計のために情報を知りたい。
- 障害者の権利: 障害を理由に命を選別されるべきではない。
この二つの権利はしばしば対立します。日本の法律は、このバランスを取るための明確な答えを出せておらず、個々のカップルの倫理的判断に委ねられているのが現状です。
4. 現在の法的課題:「無法地帯」のNIPT市場と規制の動き
これまでNIPTを直接規制する法律はありませんでした。これまでは日本産科婦人科学会(日産婦)という一学術団体が自主規制(指針)を行い、認定施設を管理してきました。しかし、ここにも法的な限界が露呈しています。
認可施設と認可外(無認可)施設
学会の指針を守る「認可施設」では、厳格な遺伝カウンセリングが義務付けられ、検査対象も3つのトリソミー(13, 18, 21番)に限定されています。
一方、法律による規制がないため、美容外科や皮膚科などが「認可外施設」として参入し、十分なカウンセリングなしに、全染色体検査や性別判定などを行っています。
- 認可外施設の問題点: 陽性が出た後のフォローがない、医師が産婦人科医でない、結果の解釈を誤るなどのトラブルが多発していますが、現在の法律ではこれを取り締まることができません(医師法違反等でない限り、医療行為として自由診療で行うことは違法ではないため)。
医療法改正等の動き
こうした状況を重く見た国(厚生労働省)は、NIPTを含む遺伝学的検査の質の確保に向けた法整備の検討を始めています。
具体的には、認証制度を国の関与の下で行い、質の低い施設を淘汰し、妊婦が正しい情報と適切なカウンセリングを受けられる体制を「法律」または「国の指針」として整備しようとする動きです。
しかし、「検査を受ける権利の制限になる」との反対意見もあり、完全な法制化には至っていません。現時点では、学会と国が連携した新認証制度がスタートしていますが、依然として法的強制力のないガイドラインベースの運用にとどまっています。
5. 知的障害児の「生」を支える法律:障害者総合支援法
NIPTの結果、陽性であっても出産を選択するご家族もいらっしゃいます。また、検査では分からなかった障害を持って生まれるお子さんもいます。
「産んだ後の法律」について知ることも、NIPTを考える上で不可欠です。
障害者総合支援法
日本には、障害のある人々の生活を支えるための「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」があります。
この法律に基づき、以下のようなサービスが「権利」として保障されています。
- 居宅介護(ホームヘルプ): 自宅での入浴や食事の介助。
- 児童発達支援: 未就学児への療育サービスの提供(利用者負担の無償化が進んでいます)。
- 就労移行支援: 一般企業への就職に向けたトレーニング。
- グループホーム: 地域での共同生活援助。
児童福祉法と特別児童扶養手当法
- 児童福祉法: 障害児通所支援(放課後等デイサービスなど)を規定し、親の就労と子供の発達を支援します。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律: 重度・中度の障害児を養育する保護者に手当を支給し、経済的負担を軽減します。
かつての「家族だけで抱え込む」時代から、法律に基づいた「社会全体で支える」仕組みへと、日本の法制度は確実に進化しています。「法律」は中絶を規制するだけでなく、生まれた命を守るための強力なセーフティネットとしても機能しています。
6. まとめ:法律は「最低限のルール」。決断は「あなた」の中に。

本記事で解説してきた通り、NIPTと知的障害を巡る日本の法的状況は、歴史的経緯と現代の倫理観が絡み合い、非常に複雑です。
- 中絶の法的根拠: 「胎児の障害」を理由とする条文はなく、実質的には「経済的理由」として運用されている(グレーゾーン)。
- 優生思想: 旧優生保護法の反省から、国は「障害児の出生防止」を目的とした政策はとれない。
- 国際的視点: 障害者権利条約により、安易な選別に対する監視の目は厳しくなっている。
- 規制の現状: NIPT実施施設を直接取り締まる法律はなく、学会指針と国の関与による緩やかな統制にとどまる。
NIPTを受けること、そしてその結果を受けてどのような決断を下すかについて、法律は明確な「正解」も「禁止」も提示していません。法が沈黙している領域(グレーゾーン)だからこそ、そこには個人の「倫理」と「価値観」が問われます。
法律を知ることは重要です。しかし、法律はあくまで社会の最低限のルールに過ぎません。
「法的に許されるか」だけでなく、「自分たちの家族にとって何が最善か」「生命とどう向き合うか」という問いに対しては、臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーとの対話(遺伝カウンセリング)を通じて、時間をかけて答えを出していく必要があります。
NIPTは単なる検査ではありません。それは、法と倫理、そして親としての覚悟が交差する、人生の重大な選択の場なのです。