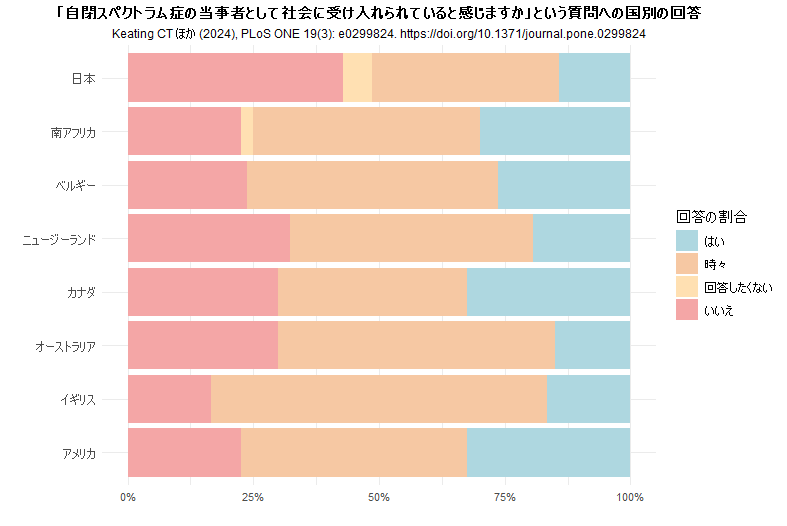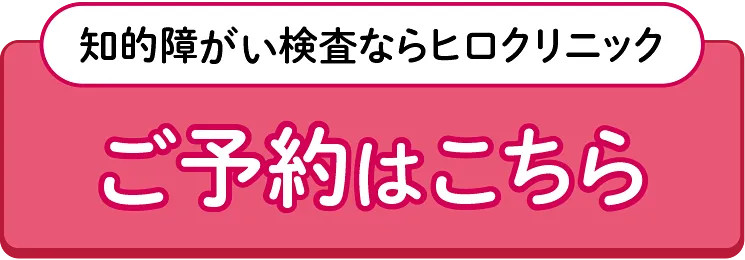やさしいまとめ
本記事は「「ふつう」に見せる努力:自閉スペクトラム症と日本のカモフラージュ(後編)」です。前編では、自閉スペクトラム症(ASD)の方が日常生活で行う「カモフラージュ(camouflaging)」の背景や心理的影響、特に日本文化に根ざした過剰適応の実態について紹介しました。
後編では、そのカモフラージュがどのように社会的評価や支援に影響を与えるか、性別やジェンダー、スティグマとの関係、そして「構造的な問題」としてどう捉え直すべきかを掘り下げます。研究データと当事者の語りを交えながら、「ふつうに見える」ことの裏にある努力と孤独、そして変革の可能性に迫ります。
第6節 カモフラージュの「評価」はなぜ難しいのか――成果、努力、そして「ふつう」の罠
カモフラージュのもっともやっかいな側面は、「うまくやっているように見える」ことかもしれません。
学校では成績が良い。
職場では指示に従って動けている。
笑顔も、会話も、自然にこなしているように見える──。
けれど、その「自然さ」は、日々の努力と緊張のうえに築かれた仮面であることがあります。
そしてその努力が見えないぶん、支援の必要性が過小評価されてしまうのです。
「できるように見える」と「できる」は違う
当事者からは、こんな声が聞かれます。
「“問題ないですよね”って言われた。でも、それは毎日仮面をつけてたから」
「できているって思われることが、いちばんつらい」
「やればできるけど、やるたびにすごく疲れる」
表面的な“できている感”があるほど、本当の苦しさは見えにくくなる。
そしてそれは、周囲だけでなく、本人自身にも、「大丈夫なふり」を求める圧力となってのしかかります。
支援が「成果」に縛られるとき
教育や福祉の場では、「できることが増えたか」がしばしば支援の尺度になります。
人前で話せるようになった、自己紹介ができるようになった、グループに参加できた──。
けれども、それが当人の安心や快適さにつながっているかどうかは、また別の話です。
むしろ、「ふつうに見えること」を目的とした支援は、
結果として、さらに深いカモフラージュを求める構造を強化してしまうことがあります。
Haradaら(2024年)の調査にも、こうした証言が記録されています。
「“ふつうに見えた”ことで褒められたけど、本当は毎日がつらかった」
「支援を求めたら、『もう治ったんじゃないの?』って言われた」
「努力できる人」こそ見落とされるリスク
努力できる人は大丈夫──
そう思われがちですが、カモフラージュの世界では、努力できる人ほど、深く傷ついていることがあるのです。
支援が必要なのは、「できない人」だけではありません。
「できているように見えるけれど、限界に近い人」こそ、もっとも声を上げにくく、見えにくいリスクを抱えています。
そして何よりも──
努力し続けなければ“居場所を失う”という状況こそが、
本人の心を追い詰めているのです。
第7節 カモフラージュは誰に向けて行われるのか── 社会的応答性とダブル・エンパシー
カモフラージュという行動は、これまで「定型社会に適応するための戦略」として説明されることが多くありました。
たしかに、非自閉の他者からの評価や偏見に備える行動として、カモフラージュが発達していく側面はあります。
けれども近年の研究は、それだけでは語りきれない、より繊細な現実を示しはじめています。
カモフラージュは、単なる防御ではありません。
それはしばしば、「関係を築くため」「嫌われたくないという気持ちから」「相手に安心してほしいという願いから」行われるものでもあるのです。
自閉スペクトラム症同士でも、カモフラージュは起きる
2024年に発表された日本の研究(Funawatariら)は、「誰に対してカモフラージュが行われるのか」という問いを正面から扱いました。
驚くべきことに、参加者たちは「非自閉的に見える人」に対してよりも、「自閉的な特徴があると見られる人」に対して、より強いカモフラージュを行っていたという結果が得られました。
この知見は、「カモフラージュ=定型社会への適応」という従来の前提に、大きな問いを投げかけます。
つまり、カモフラージュは「社会的な多数派に合わせるため」だけではなく、
「相手との関係をどう築きたいか」「どう見られたいか」といった感情や関係性に強く左右されている可能性があるのです。
たとえば、相手が初対面である場合、あるいは同じ診断名を持っていても、信頼関係ができていない場合には、
「この人にも変だと思われたくない」「傷つけたくない」という思いから、つい自分を調整してしまう。
それは、安心できる関係を築くまでの一時的な努力であり、
「親密さ」や「脆弱さ」への配慮と深く結びついた行動だといえるでしょう。
「わかってもらえない」ことの、すれ違い
こうした視点は、「ダブル・エンパシー問題(double empathy problem)」という理論と重なります。
この理論では、自閉スペクトラム症の人と非自閉の人とのあいだのコミュニケーション困難は、
一方的な「社会性の欠如」からではなく、「相互の理解の前提や期待のずれ」によって起きるとされています。
つまり、「わからない」のはどちらか一方ではなく、
どちらの側にも、すれ違いの理由がある。
この考え方に立つと、カモフラージュは「理解してもらえない痛み」に対する反応であると同時に、
「相手と関係を築くための工夫」としての意味も帯びてきます。
模倣や沈黙の背後には、必ず、相手を見つめようとする眼差しがある。
だからこそ、カモフラージュは「他者とのつながりを求める行動」でもあるのです。
「素のままでいられる関係」の希少さ
Haradaら(2024年)の質的研究には、自閉スペクトラム症の当事者グループに初めて参加したハルコさんの語りが紹介されています。
彼女は、「やっと自分を出せる場所が見つかった」と述べ、それまでの生活ではどこでも「ふるまいの調整」が必要だったと振り返ります。
その体験は、仮面を下ろせることの大きさ──
そして、それがいかに希少であるかを、静かに物語っています。
しかし一方で、同じ診断名を持つ人が相手であっても、初対面の場面ではやはりカモフラージュしてしまうという声も多く聞かれました。
つまり、「素でいられること」は、診断名の一致だけでは保証されません。
信頼、理解、そして安心できる空気──
そうした土台があってこそ、人は少しずつ仮面を外せるのです。
「迷惑をかけない」という文化的規範
日本では、「人に迷惑をかけない」「空気を乱さない」という価値観が強く浸透しています。
それは、周囲への配慮や協調を大切にする美徳である一方で、
「自分を抑えてでも合わせる」ことを当然と感じさせる力にもなります。
そのため、たとえ相手が同じく自閉スペクトラム症であったとしても、
「変だと思われたくない」「負担をかけたくない」という気持ちから、自然とカモフラージュが生じてしまう。
安心していられるはずの場所でも、
「相手のために」自分を抑えるという行動が、自発的に起こるのです。
けれども──
いったん信頼が築かれると、カモフラージュは少しずつ薄れていきます。
これは、カモフラージュが「本質的な特性」ではなく、
「環境が求めた応答」だということを、はっきりと示しています。
第8節 スティグマ、アイデンティティ、孤独感
カモフラージュは、しばしば「努力」や「工夫」として語られます。
けれども実際には、それは社会からの圧力への応答であり、周囲の無理解や排除が生んだ適応行動です。
なぜ人はカモフラージュを身につけるのか。
その理由を理解するためには、個人の内面だけでなく、取り巻く文化や環境に目を向ける必要があります。
なかでも、もっとも深く影響を与えるのが、スティグマ(stigma)と孤独(loneliness)です。
スティグマが生む沈黙
スティグマとは、社会的に望ましくないとみなされた属性に対して与えられる、否定的なラベルです。
自閉スペクトラム症の人がカモフラージュを選ぶ背景には、
「本当の自分を見せたら排除されるのではないか」
「誤解されて、過小評価されてしまうのでは」
という、切実で現実的な恐れがあります。
それは自己否定ではなく、他者からの反応を予期した防衛。
日本の文化では特に、「診断を明かすこと」が「空気を悪くする」「面倒な存在と見なされる」と受け取られやすく、沈黙がルールとなる場面もあります。
Fukushimaら(2025年)の研究では、自閉スペクトラム症の診断を開示した大学生が、そうでない学生よりも周囲から距離を置かれる傾向があると報告されています。
行動に差がなかったとしても、「診断を伝えた」という事実だけで態度が変化するのです。
これは、診断の開示が偏見を減らすどころか、新たな偏見を引き起こすという、苦しい逆説を映し出しています。
「私は負担なのではないか」という内なる声
スティグマは、外から与えられるものにとどまりません。
やがて内面にも染み込んでいきます。
Guanら(2025年)は、「アイデンティティ条件性(identity contingencies)」という概念を提唱しました。
それによれば、日常のなかで繰り返されるささやかな差別(マイクロアグレッション)が、他者からの受容感を下げ、孤独感を強め、結果としてカモフラージュ行動を強化するのです。
特に強まるのは「同化(assimilation)」です。
つまり、自分の特性を隠すだけでなく、定型のふるまいを積極的に真似る傾向が強まります。
それは自己否定ではなく、
「所属するために選んだ方法」
「関係を壊さないための戦略」でもあります。
興味深いのは、「自己受容の高さ」とカモフラージュの強さにはあまり関係がなかったという点です。
自分を肯定できていても、社会から拒絶されるかもしれないという予測があるだけで、人は自然にカモフラージュしてしまうのです。
孤独という副作用
孤独はどんな文化にも存在します。
しかし、集団主義が強い文化では、ときにより深い道徳的な痛みを伴います。
日本では、「集団の一部であること」が当然とされ、「そこから外れること」はしばしば否定的に評価されます。
「出る杭は打たれる」という言葉のとおり、たとえ目立たない違いであっても、沈黙と自己抑制が求められる場では、排除の対象となり得るのです。
カモフラージュは、そんな社会に「つながり続けるための技術」となります。
けれどもその代償として、自分を見失い、仮面をかぶり続ける日々が続きます。
ある日本の参加者はこう語りました。
「仕事では『別の人格』を演じている感覚があった。
自分と役割を完全に切り離していた。でも、それが限界になった。」
この言葉は、表面的な適応の裏にある、深い断絶と疲れを物語っています。
第9節 カモフラージュを「個人の工夫」ではなく「構造の問題」として捉える
カモフラージュは、長らく「本人の努力」や「対処スキル」として語られてきました。
けれども近年では、その必要性そのものが、社会構造のミスマッチから生じているのではないかという視点が、当事者・臨床家・研究者のあいだで広がりつつあります。
問題は「特性」ではなく「環境」
たとえば、自閉スペクトラム症の人が見せる、率直な話し方や繊細な感覚、特定の興味への集中。
それらは、ある環境では強みになり、別の環境では「障害」とみなされてしまう。
違いが問題になるのは、それを許さない文化や組織の側にあります。
学校での厳格な振る舞いの指導。
職場での一律的なコミュニケーションへの期待。
家庭内でさえ、「そのままの振る舞い」が不適切とされることがあります。
そのような場で、人は「ありのまま」では生きづらくなり、カモフラージュという手段を選ばざるを得なくなるのです。
自分を否定したからではなく、生き延びるためにそうした──この視点を忘れてはなりません。
特に日本社会では、空気を読み、直接的な表現を避け、集団に調和することが求められます。
目には見えない期待に応えるうちに、人は自分でも気づかぬうちに、仮面を形づくっていきます。
「ふつうに見えること」をゴールにしてはいけない
従来の支援や療育は、「社会適応」を目的としてきました。
けれどもそこで目指されてきたのは、しばしば定型に近づくことでした。
姿勢や視線の使い方、感情の表現方法、身体の動きを抑えるトレーニング──。
それらは一見、社会的スキルの習得のように見えても、実際にはカモフラージュの強化につながることがあります。
Haradaら(2024年)の調査では、次のような声が寄せられています。
「“普通に見えた”ことで褒められたけど、本当は毎日がつらかった」
「職場で配慮を求めたら、『もう回復したんじゃないの?』って言われて、支援がなくなった」
外から見える「適応」が評価基準になると、仮面をかぶり続けなければ支援が得られないという矛盾が生まれてしまいます。
環境との接点を、あらためて設計しなおす
こうした課題に対して近年注目されているのが、生態学的適合(ecological fit)の考え方です。
これは、「人が環境に合わせる」のではなく、環境のほうが認知スタイルの多様性に応じて変化すべきだという視点です。
たとえば、文化的カモフラージュを前提としたより繊細な診断評価の導入。
感覚刺激や非言語的表現の自由が認められる学校環境。
表現方法にこだわらない職場の評価制度。
そして、見せかけだけではない実効性ある合理的配慮と法的保護。
そのすべてに共通するのは、「誰かのために変えてあげる」という発想ではなく、多様な人が最初から前提に含まれている社会設計です。
特に重要なのは、支援の設計段階から、当事者を「対象者」ではなく「共同設計者」として迎えること。
これは理想論ではなく、現実的な鍵となる考え方です。
「貢献する当事者」としての再定位
長年、自分の特性を理解されずにきた人たちが、いまようやく、自らの経験を再解釈しはじめています。
たとえば、ハルコさん。
彼女は自身の体験をもとにアート作品を制作し、同じように「見えにくさ」に悩む人々の共感を呼び起こしました。
支援者ではなく、表現者として社会とつながるその姿は、
「自閉スペクトラム症という在り方そのものが、社会にとっての貢献になりうる」ことを静かに教えてくれます。
また、「後輩を支えたい」「文化に合った新しい支援のかたちを提案したい」という声も多く聞かれます。
それは、カモフラージュの必要が少ない社会をつくるための、はじめの一歩です。
第10節 おわりに ―「偽り」ではなく「生きるため」のカモフラージュ
カモフラージュは、誰かをだますための行動ではありません。
カメレオンが背景に溶け込むように、それは「生きるための調整」です。
ときに創造的で、ときに苦しく、それでも常に現実に即した応答です。
とくに日本のように、「違い」が見えにくくされがちな文化では、
カモフラージュは生き延びる技術として身につけられます。
でもそれは、生きやすさと同じではありません。
本稿では、カモフラージュを「行動」ではなく、社会との関係性の中で生まれ、強化され、代償を伴うものとして描いてきました。
文化的規範──調和、間接性、序列──は、学校、職場、家庭のあらゆる場面で、その形を変えて作用しています。
研究は示しています。
カモフラージュは、診断の遅れや誤診を引き起こし、支援を妨げ、メンタルヘルスに影響を及ぼす。
そして自己の断絶や、深い孤独へとつながる可能性があることを。
それでも、すべてのカモフラージュが否定されるべきものではありません。
文化によっては、中程度のカモフラージュが一時的な安定をもたらすこともあります。
その評価は一様ではないのです。
でも、ひとつだけはっきりしていることがあります。
カモフラージュの存在は、内面の弱さではなく、環境との不整合を示しているという事実です。
カモフラージュは、「自分らしさの欠如」ではありません。
それは、「自分らしさが受け入れられないときに選ぶ、最後の手段」です。
だからこそ、変わるべきは、個人ではなく、構造です。
もっと多様な「普通」が認められる社会へ。
違いが危険とされない社会へ。
「理解させる」のではなく、「ともに理解を育てる」社会へ。
ハルコさんが語った言葉が、静かにその道しるべとなります。
「誰かが“ちゃんと見てくれる”だけで、心が軽くなるんです。」
そのやさしい願いが、カモフラージュを必要としない未来への、もっとも確かな一歩なのかもしれません。
引用文献|References
- Mandy, Will. ‘Social Camouflaging in Autism: Is It Time to Lose the Mask?’ Autism, vol. 23, no. 8, Nov. 2019, pp. 1879–81. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1177/1362361319878559
- Hull, Laura, et al. ‘Gender Differences in Self-Reported Camouflaging in Autistic and Non-Autistic Adults’. Autism, vol. 24, no. 2, Feb. 2020, pp. 352–63. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1177/1362361319864804
- Funawatari, R., Sumiya, M., Iwabuchi, T. et al. Camouflaging in Autistic Adults is Modulated by Autistic and Neurotypical Characteristics of Interaction Partners. J Autism Dev Disord (2024). https://doi.org/10.1007/s10803-024-06481-5
- Guan, Siqing, et al. Understanding Autistic Identity Contingencies: The Chain Mediation Effect of Autism Acceptance and Loneliness in Ableist Microaggressions and Social Camouflage. 4 Feb. 2025. In Review, https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5945464/v1
- Fukushima, Yasuko, et al. ‘Stigmatizing Attitudes toward Autistic Students: A Cross‐sectional Vignette Survey among Japanese University Students’. Japan Journal of Nursing Science, vol. 22, no. 2, Apr. 2025, p. e70008. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1111/jjns.70008.
- Harada, N., Pellicano, L., Kumagaya, S., Ayaya, S., Asada, K., & Senju, A. (2024). “I don’t think they understand the reality of autism”: the lived experiences of late-diagnosed autistic adults in Japan. https://osf.io/my3r9/download
- Oshima, F., Takahashi, T., Tamura, M. et al. The association between social camouflage and mental health among autistic people in Japan and the UK: a cross-cultural study. Molecular Autism 15, 1 (2024). https://doi.org/10.1186/s13229-023-00579-w
- Tamura, Masaki, et al. ‘Understanding Camouflaging, Stigma, and Mental Health for Autistic People in Japan’. Autism in Adulthood, vol. 7, no. 1, Feb. 2025, pp. 52–65. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1089/aut.2023.0035
- Atherton, Gray, et al. ‘Does the Study of Culture Enrich Our Understanding of Autism? A Cross-Cultural Exploration of Life on the Spectrum in Japan and the West’. Journal of Cross-Cultural Psychology, vol. 54, no. 5, Aug. 2023, pp. 610–34. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1177/00220221231169945