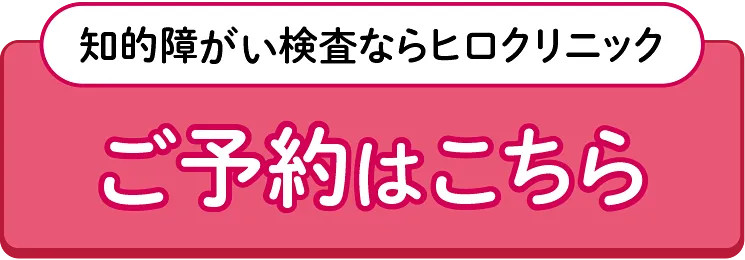「NIPTを受ければ、自閉症などの発達障害も分かる」と誤解していませんか? 結論から言えば、NIPTで分かるのは「染色体異常に起因する知的障害」であり、自閉スペクトラム症やADHDなどの「発達障害」は診断できません。本記事では、多くの人が混同しやすいこの2つの違いと、なぜ現代医学でも発達障害の出生前診断が不可能なのか、その医学的根拠を明確に解説します。
1. 「知的障害」と「発達障害」の医学的な違いと定義
NIPTの有効範囲を理解するためには、まず対象となる「障害」が医学的にどう定義されているか、その違いを明確にする必要があります。これらは重なり合う部分もありますが、診断基準や原因においては異なる概念です。
知的障害(Intellectual Disability)とは
知的障害は、主に「知的機能」と「適応機能」の2つの側面から診断されます。
- 知的機能: 知能検査(IQ)によって測定され、一般的にIQ70以下が目安となります。記憶力、思考力、計算能力、問題解決能力などに制約が見られます。
- 適応機能: 日常生活を送る能力、社会的なルールを守る能力、コミュニケーション能力などを指します。
- 原因: 染色体異常(ダウン症候群など)、周産期のトラブル(低酸素脳症など)、感染症、原因不明など多岐にわたります。NIPTがターゲットにしているのは、このうち「染色体異常に起因するもの」です。
発達障害(神経発達症:Neurodevelopmental Disorders)とは
発達障害は、脳機能の働き方の偏りによって生じる行動やコミュニケーションの特性を指します。重要なのは、必ずしも知的障害(IQの低さ)を伴うわけではないという点です。
- 自閉スペクトラム症(ASD): 対人関係の難しさ、こだわり、感覚過敏など。
- 注意欠如・多動症(ADHD): 不注意、多動性、衝動性など。
- 学習障害(LD): 全体的な知能に遅れはないが、読み書きや計算など特定の学習のみが極端に苦手。
これらは生まれつきの脳の特性ですが、原因は単一の遺伝子ではなく、多数の遺伝子と環境要因が複雑に絡み合っている(多因子遺伝)と考えられています。
二つの障害の重なり(オーバーラップ)
ここが話をややこしくする点ですが、「知的障害を伴う自閉スペクトラム症」というケースも存在します。また、ダウン症候群(知的障害がある)の子供が、ASDのようなこだわり行動(発達障害の特性)を併せ持つこともあります。
NIPTはこの複雑な相関関係のうち、「染色体の数」という物理的な変化が原因である部分だけをスクリーニングする検査なのです。
2. NIPTで「分かる」知的障害と「分からない」発達障害
では、具体的にNIPTの結果はこれらの障害とどう結びついているのでしょうか。検査の仕組みからその限界を紐解きます。
NIPTで高精度に検出できる「染色体起因の知的障害」
NIPT(基本検査)は、母体血中の胎児由来DNA断片を解析し、特定の染色体の本数を調べます。
- 21トリソミー(ダウン症候群):
21番染色体が3本ある状態です。ダウン症候群は、ほぼ全例において軽度から中等度の「知的障害」を伴います。したがって、NIPTで21トリソミー陽性と判定され、確定診断がついた場合、生まれてくる子供には高い確率で知的障害があることが予測されます。 - 18トリソミー、13トリソミー:
これらも重度の知的障害を伴います。
つまり、「染色体の本数の異常によって引き起こされる知的障害」に関しては、NIPTは非常に有効な予測ツールとなります。これが「NIPTで知的障害が分かる」と言われる所以です。
なぜNIPTで「発達障害(ASD/ADHD)」は分からないのか
一方で、一般的な自閉スペクトラム症やADHDは、NIPTでは検出不可能です。理由は大きく分けて3つあります。
- 原因の特定が困難(多因子遺伝):
発達障害の多くは、たった一つの染色体や遺伝子の異常で決まるものではありません。数百、数千という遺伝子のわずかなタイプ(多型)の組み合わせと、妊娠中の環境、出産時の状況、生後の環境などが複雑に作用して発現します。特定の「自閉症染色体」や「ADHD遺伝子」が存在するわけではないため、DNAを調べても診断できません。 - 診断基準が「行動観察」であること:
そもそも発達障害の診断は、血液検査やMRI画像で行うものではなく、医師による問診と行動観察によって行われます。「目が合わない」「言葉が遅い」「じっとしていられない」といった症状は、生後数年経って初めて明らかになるものです。胎児の段階でこれらを予測するバイオマーカー(生体指標)は、現代医学では確立されていません。 - NIPTの解像度の限界:
通常のNIPTが見ているのは「染色体の本数」という、遺伝情報の中では非常に大きな枠組みです。発達障害に関与しているかもしれない微細な遺伝子配列の違いまでは、この検査では読み取ることができません。
したがって、「NIPTが陰性だった=発達障害の子は生まれない」という保証には全くなりません。この点は強く認識しておく必要があります。
3. グレーゾーンの解説:微小欠失検査と発達障害リスク
近年、認可外施設などを中心に、検査範囲を拡大した「全染色体検査」や「微小欠失検査」が行われています。これらは発達障害と関連があるのでしょうか?
微小欠失症候群と発達障害の関連性
染色体の本数は正常でも、染色体の一部がごくわずかに欠けている状態を「微小欠失」と呼びます。一部のNIPTオプション検査ではこれらを検出できます。
例えば、以下の疾患は発達障害的な特性や精神疾患のリスクを伴うことが知られています。
- 22q11.2欠失症候群(ディジョージ症候群):
心疾患などの身体症状に加え、学習障害や軽度の知的障害が見られることが多いです。また、学齢期以降に統合失調症や自閉スペクトラム症(ASD)を発症するリスクが、一般よりも高いことが分かっています。 - 15q11-q13欠失(プラダー・ウィリ症候群 / アンジェルマン症候群):
重度の知的障害や、過食、特有の行動障害(発達障害的行動)を伴います。
これらの特殊なケースにおいては、「NIPT(微小欠失検査)によって、将来の発達障害リスクが高い疾患が見つかる」という可能性はゼロではありません。
拡大検査の注意点と「偽陽性」
「それなら詳しく調べたほうがいいのでは?」と思われるかもしれませんが、専門家の多くは安易な拡大検査に慎重です。
微小欠失は非常に稀な疾患であるため、NIPTでの検査精度(陽性的中率)が著しく低下します。「陽性」と出ても、実際には誤り(偽陽性)である可能性が高く、不必要な羊水検査や過度な不安を招くリスクがあるからです。
また、微小欠失が見つかったとしても、実際にどの程度の障害が出るか(表現型)は個人差が激しく、生まれてみないと分からない部分が大きいのも事実です。
4. 誤解されがちな「ダウン症候群」の性格と発達特性
「知的障害」と「発達障害」の違いを考える上で、NIPTで最も多く見つかるダウン症候群の子供たちの「発達のリアル」を知ることも重要です。
「ダウン症=いつもニコニコ」だけではない
一般的にダウン症候群の子供は「明るい」「人懐っこい」「音楽が好き」といった性格特性(行動表現型)を持つと言われます。これは多くの親御さんにとって救いとなるポジティブな要素です。
しかし同時に、以下のような発達障害的な特性を持つこともあります。
- 頑固さ(固執性): 自分のペースを崩されるのを極端に嫌う。
- 多動・衝動性: 興味のあるものに突進してしまう。
- 自閉的傾向: 一部のダウン症児(約5〜10%程度という報告もあり)は、自閉スペクトラム症を合併していると診断されます。
つまり、NIPTで分かるのは「ダウン症候群である(21番染色体が多い)」という事実だけであり、その子が「育てやすい性格か」「自閉傾向があるか」「どの程度の知的レベルか」といった個人のキャラクターまでは予測できません。
染色体はあくまで「設計図の表紙」であり、その中身の物語は一人ひとり全く異なるのです。
5. NIPTを受ける前に整理すべき「心の準備」

ここまでの解説で、NIPTは「万能な予言書ではない」ことがお分かりいただけたかと思います。では、私たちはこの検査とどう向き合えばよいのでしょうか。
「分からないこと」を受け入れる覚悟
妊娠・出産は、そもそも不確実性に満ちた営みです。
NIPTですべての染色体が正常(陰性)であっても、出産時のトラブルで脳性麻痺になることもあれば、成長してから自閉スペクトラム症や学習障害が判明することもあります。また、病気や事故のリスクもあります。
「絶対に障害のない子が欲しい」という願いは切実ですが、現代の医療をもってしても、それを100%保証することは不可能です。
NIPTを受ける際は、「分かること(染色体異常)」を確認するために受けるのであって、「すべてをクリアにするため」に受けるものではないと割り切る必要があります。
陽性だった場合のシミュレーション
もし検査を受け、ダウン症候群などの陽性判定が出た場合、ご自身たちがどうしたいか、事前にパートナーと話し合っておくことが大切です。
「知的障害があっても育てる環境があるか」
「療育や支援制度はどうなっているのか」
「検査結果がどうあれ、迎え入れる覚悟があるのか」
あるいは、「今は育てる自信がないから、検査を受けて判断したい」という考えも、一つの正直な親心であり、否定されるべきではありません。重要なのは、検査の限界を知った上で、自分たちの価値観に基づいて選択することです。
遺伝カウンセリングの重要性
インターネット上には、「NIPTで発達障害も分かる」と誤認させるような広告や、不安を煽る情報が溢れています。
正確な知識を得るためには、臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーが在籍する医療機関で、しっかりとした「遺伝カウンセリング」を受けることを強くお勧めします。
専門家は、あなたの不安(発達障害への懸念など)を汲み取った上で、NIPTで何が分かり、何が分からないのか、そしてその不安にどう対処すべきかを、医学的・心理的側面からサポートしてくれます。
6. まとめ:NIPTは「命の選別」か「未来への準備」か
本記事のポイントをまとめます。
- NIPTで分かること:
ダウン症候群(21トリソミー)などの染色体数の異常。これらは高い確率で「知的障害」を伴います。 - NIPTで分からないこと:
自閉スペクトラム症(ASD)、ADHD、学習障害(LD)などの「発達障害」。これらは遺伝要因と環境要因が複雑に関与するため、出生前診断は不可能です。 - 注意点:
微小欠失検査で一部の発達障害リスク(22q11.2欠失など)が分かる場合もありますが、精度や偽陽性の問題があり、解釈には高度な専門知識が必要です。 - 結論:
NIPT陰性は「発達障害がないこと」の証明にはなりません。
子供の発達や個性は、染色体という「ハードウェア」だけで決まるものではありません。育つ環境、親との関わり、教育といった「ソフトウェア」との相互作用で、無限に変化していくものです。
たとえ障害があったとしても、早期からの適切な療育(発達支援)を受けることで、その子の可能性は大きく広がります。
NIPTは、あくまでお腹の赤ちゃんの「一面」を知るためのツールに過ぎません。検査結果に振り回されるのではなく、その情報をどう使い、どう準備し、これから生まれてくる命とどう向き合うか。その主体的な意思決定こそが、親になるための第一歩と言えるのではないでしょうか。